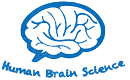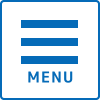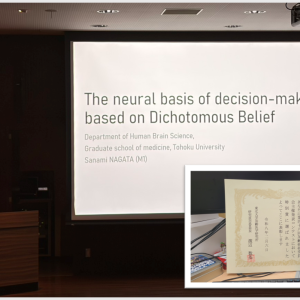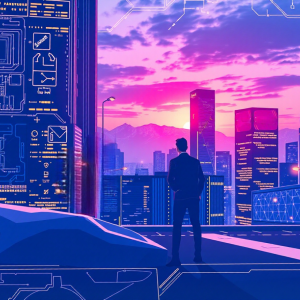脳を知れば人間がわかる。
世界はもっとよくなる。

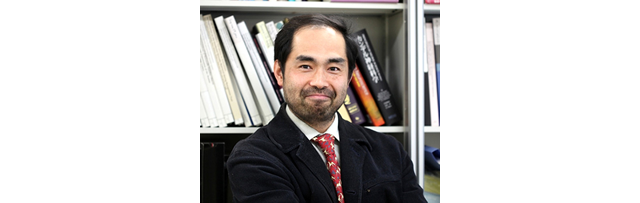
杉浦 元亮Motoaki Sugiura
東北大学 教授
加齢医学研究所 人間脳科学研究分野
災害科学国際研究所 認知科学研究分野
応用認知神経科学センター 研究教育戦略部門
スマート・エイジング学際重点研究センター
認知脳機能研究部門
脳を知れば人間がわかる。
世界はもっとよくなる。
人間らしい精神・行動、そして社会は、脳のどんな仕組みで実現されるのでしょう。私たちはその秘密を解明する「人間脳科学」を展開しています。脳機能画像と生理・行動計測、社会調査を駆使し、基礎から応用まで人間性に関わるあらゆる学問領域をつなぐ「ハブhub」となる脳科学を目指します。みなさまのご参加をお待ちしています。
研究テーマ
-
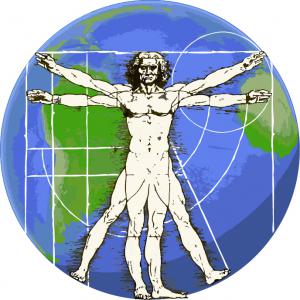
自己を創る脳
「自己」は脳でどのように生まれ、我々の認識や行動、適応性にどう影響を及ぼすのでしょう。身体・運動・社会性・メンタルヘルスなど、自己の多様な側面について、謎の解明
-

価値はどこから生まれるか
脳は多様な感覚入力を統合し、知識・記憶を参照して事物や環境の価値を評価しますが、その過程はまだ謎だらけです。様々な行動実験・脳計測実験から、その不思議な実態が明
-

言葉とコミュニケーション
人間はコミュニケーションによって社会を作り、言葉はその強力なツールとして気持を伝え人を動かします。これらの機能とその獲得の脳内基盤の解明は、人間理解と教育応用へ
-

災害と生きる力
災害における人間の心と行動について様々な研究を行っています。 特に東日本大震災(2011)の被災者を対象とした調査で「災害を生きる力」の8因子(リーダーシップ
-

未来を拓く人間脳科学
超高齢社会・災害の多発・スマート社会。環境や社会の変化は我々の生活や価値観をどう変えるのでしょうか。認知・脳科学の視点から、人間らしい生き方、技術や社会のあり方
ニュース
-
202602.06できごと
社会的文脈における自己評価: 社会的受容と拒絶が自己に与える影響(加齢医学研究所研究奨励賞)
このたび、第165回加齢医学研究所研究奨励賞を受賞いたしました。 本受賞に関連して、自己評価が社会生活の中でど
-
202602.01研究
防災教育の「盛り込みすぎ」は逆効果?:津波メカニズムと避難指示の併用教育効果の脳検証(論文出版)
津波のメカニズム(なぜ起こるか)と避難指示(何をすべきか)の両方を伝えることは、防災教育の効果をより高めるのでしょう
-
202511.27研究
AIフィードバックと第二言語学習者の不安(国際学会ポスター発表)
生成 AIとの対話が第二言語(L2)学習に広く取り入れられていますが、AI からのフィードバックが学習者の不安や脳活
-
202511.22研究
慰めで大事なのは、話し方だけじゃない?"同期"の重要性とは(論文出版)
対人感情の調整というと、「人を慰めるには話し方が大事だ」と思われがちですが、研究によると、実は身体や脳の同期も重要な
-
202511.14できごと
Language, Testing, and the Brain: A Neurolinguistic Approach to Learning and Assessment
言語はどのように学習され、どのように評価されるのでしょうか。 本セミナーでは、応用言語学・言語テスティング・認知神
-
202511.05研究
感染の怖さは我々の社会性をどう変化させるのか (論文出版)
感染の怖さは他人または社会との関わり方に根本的な変化をもたらすでしょうか。疫学や社会心理学で議論されてきたこの問いは
-
202510.28できごと
【セミナー】Gestures, Language & Brain Dynamics
ジェスチャーは、私たちが言語を理解・処理する脳にどのような影響を与えるのでしょうか。 本セミナーでは、言語学と神経
アクセス
東北大学加齢医学研究所(IDAC)
〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1
スマート・エイジング棟3F
E-mail: hubs@grp.tohoku.ac.jp